はじめに
「睡眠は1日7〜8時間が理想」とよく言われます。多くの健康ガイドラインでも、これが推奨される標準的な睡眠時間とされています。実際、十分な睡眠は認知機能、免疫力、メンタルヘルス、長寿など、あらゆる側面に良い影響を与えることが科学的に示されています。しかし、世の中にはこの常識に当てはまらない人が存在します。
たとえば、1日わずか45分の睡眠で10年以上にわたって活動を続けている人物──ショートスリーパーの堀大輔氏は、その代表例です。日中に眠気を感じることもなく、フルタイムの仕事や自己表現活動を精力的にこなしている彼の存在は、「人間は皆7〜8時間の睡眠を必要とする」という常識に疑問を投げかけます。
本記事では、このような極端なショートスリーパーという存在を起点に、一般的な睡眠の科学から、遺伝的背景、そしてエピジェネティックな要因や進化的視点に至るまで、多面的に「睡眠の個人差」について探っていきます。
一般的な睡眠の科学
睡眠の推奨時間と根拠
アメリカ疾病予防管理センター(CDC)や日本の厚生労働省など、多くの公的機関は成人に対して「1日7〜9時間の睡眠」を推奨しています。この基準は、主に疫学研究に基づいており、睡眠時間と死亡率や疾病リスクとの関係が統計的に示されたものです。たとえば、7時間睡眠群は心疾患、2型糖尿病、うつ病、認知症などの発症率が最も低く、それ以下でもそれ以上でも健康リスクが増加することが知られています。
このような研究は、数千人〜数十万人規模の調査データをもとにしており、睡眠と健康の関係を示す上で強い信頼性を持ちます。したがって、「7〜8時間睡眠」は平均的な人にとって最も健康的な睡眠時間であるというのが現在のコンセンサスです。
睡眠の生理的役割
睡眠中、私たちの身体と脳ではさまざまな重要なプロセスが進行しています。睡眠は大きく「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」に分けられ、これらが90〜110分の周期で交互に繰り返されます。
ノンレム睡眠では深い眠り(徐波睡眠)が出現し、脳内の老廃物の除去や細胞の修復、免疫機能の調整が行われます。一方、レム睡眠中には記憶の統合や感情の整理が行われ、特に海馬と前頭前野の間での情報伝達が活発になります。さらに、グリンパティック系と呼ばれる脳の老廃物排出システムも、睡眠中に最も活性化されることが示されています。
このように、睡眠は単なる「休息」ではなく、心身のメンテナンスに欠かせない生理的プロセスです。したがって、一般的には十分な睡眠を確保することが、健康維持において重要とされています。
──では、なぜ一部の人は、これらのプロセスを極めて短時間で完了できるのでしょうか? 次のセクションでは、極端なショートスリーパーの事例を通じて、その可能性を探っていきます。
ショートスリーパーとは何者か?
堀大輔氏の事例紹介
ショートスリーパーとして注目されている堀大輔氏は、なんと1日45分という極端に短い睡眠時間で10年以上にわたって活動を続けています。彼は書籍やメディアへの出演を通じて、自らのライフスタイルを積極的に発信しており、その生活ぶりは多くの人にとって驚きと関心の対象となっています。
堀氏によれば、彼の睡眠は毎日深夜から早朝にかけての1回のみで、昼寝も含めてトータルで1時間未満。それでも日中に眠気を感じることはほとんどなく、思考も明晰で、社会生活にも支障はないといいます。通常であれば、これほどの睡眠不足は身体や精神に深刻な悪影響を与えるはずですが、彼の場合はそうした兆候が見られません。
このような極端なケースは非常に稀ではあるものの、「一律の睡眠時間がすべての人に当てはまるわけではない」という可能性を示す実例として、科学的に無視できない存在です。
既知のショートスリーパー遺伝子の存在
実際に、極端に短い睡眠でも健康を維持できる体質は、いくつかの遺伝的要因と関係していることがわかってきました。カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者Ying-Hui Fuらの研究によって、2009年に発見されたのがDEC2(BHLHE41)遺伝子の変異です。この変異を持つ人は、平均して6時間以下の睡眠でも日中の機能が損なわれず、健康を維持できると報告されています。
その後、2019年にはADRB1という別の遺伝子の変異も短時間睡眠と関連していることが報告され、複数の遺伝子が自然発生的ショートスリーパーに関与していることが示唆されています。これらの研究は、ショートスリーパーが単なる意志力や生活習慣によるものではなく、生まれつきの体質である可能性を強く支持しています。
眠っていた遺伝子がオンになる? エピジェネティクスの視点
遺伝子発現は「固定」ではない
ここで重要となるのが、**エピジェネティクス(後成遺伝学)**の概念です。従来、遺伝子は親から子へと固定的に受け継がれるものと考えられてきましたが、現在では同じDNA配列を持っていても、遺伝子の「オン/オフ」が環境要因によって調整されることが分かってきました。
例えば、ストレス、栄養状態、睡眠パターンなどの外的因子が、DNAのメチル化やヒストンの化学修飾といったメカニズムを通じて、特定の遺伝子の発現を促進または抑制するのです。つまり、誰もが潜在的に持っているショートスリーパーの要素が、何らかの環境要因によって「目覚める」可能性も理論的には考えられます。
進化的視点からの仮説
さらに興味深いのは、進化論的な観点です。人類の祖先は、原始的な環境の中で常に外敵や気候の脅威にさらされて生き延びてきました。そうした時代には、長時間の連続した睡眠をとること自体がリスクだった可能性もあり、短時間でも質の高い睡眠をとれる個体が生存に有利だった場面もあったと考えられます。
このような状況下で適応してきた遺伝子──すなわち「短時間睡眠でも機能的に行動できる遺伝子」が、進化の過程でサイレント(不活性)状態になりながらも、何らかのきっかけで現代において再び発現する可能性があるという仮説は、エピジェネティクスの観点からも十分に妥当性があります。
堀氏のようなショートスリーパーは、現代の生活環境と個人の遺伝的背景が組み合わさった結果、かつて進化の過程で一時的に選択された表現型が顕在化した例と捉えることもできるでしょう。
結論:ショートスリーパーは否定すべきか?
一般的に「1日7〜8時間の睡眠が必要」とされるのは、数多くの疫学研究や生理学的知見に基づいた、科学的に裏付けられた推奨です。睡眠不足が健康に悪影響を与えることは、数々の研究によって明確に示されています。したがって、大多数の人にとっては、このガイドラインに従うことが最も安全かつ効果的な健康戦略であることに変わりはありません。
しかしながら、堀大輔氏のようなショートスリーパーの存在、そして遺伝子変異に基づく短時間睡眠体質の実例は、「すべての人が等しく7〜8時間の睡眠を必要とする」という見方が過剰な一般化である可能性を示唆しています。
また、エピジェネティクスや進化の観点からも、個体差としてのショートスリーパーが科学的に存在しうることが支持されています。生物進化の過程において、一部の人類が短時間睡眠での生活に適応していたという仮説は、現代における極端な睡眠多様性を理解するうえで、興味深い視点を提供してくれます。
今後の視点と科学的関心
とはいえ、現在の研究の限界として、ショートスリーパー体質の長期的な健康影響については明確なエビデンスが十分とは言えません。DEC2変異やADRB1変異を持つ人々が高齢になったときの神経変性疾患リスク、免疫機能、代謝系の影響など、未知の部分が多く残されています。
また、自己申告による短時間睡眠者の中には、実際には慢性的な睡眠負債を抱えているケースもあるため、科学的検証には客観的な指標(ポリソムノグラフィーなど)を用いた慎重な調査が必要です。
今後の研究において、ショートスリーパーの遺伝的・生理学的特徴がさらに明らかになれば、個人に最適化された「パーソナライズド睡眠指導」が可能になるかもしれません。すべての人に画一的な睡眠時間を推奨するのではなく、遺伝的背景や生活スタイルに応じた柔軟な睡眠戦略が求められる時代に近づいているとも言えるでしょう。
まとめ
- 一般的な成人には7〜8時間の睡眠が科学的に推奨される。
- しかし、極端なショートスリーパーが存在することも事実。
- 遺伝子変異(DEC2、ADRB1など)や進化的背景から、その可能性は否定できない。
- とはいえ、長期的な健康影響にはまだ不明な点が多く、模倣は推奨されない。
今後も、ショートスリーパーに関する研究が進むことで、「睡眠」という私たちの生活の根幹にある営みについて、より深く理解できるようになることが期待されます。
参考文献
- Fu, Y. H., et al. (2009). “A mutation in a period gene associated with familial advanced sleep phase syndrome.” Science.
- He, Y., et al. (2019). “A genetic mechanism for the short sleep phenotype in humans.” Neuron.
- Walker, M. (2017). Why We Sleep. Scribner.
- 日本睡眠学会. (2023). 『睡眠障害の診療ガイドライン』


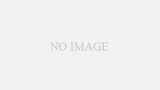
コメント